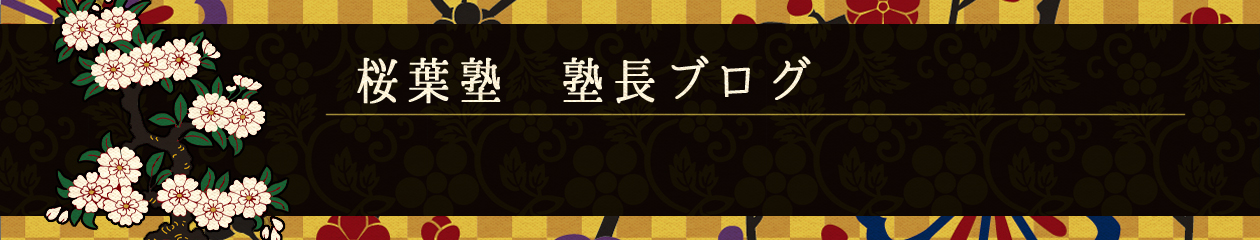人の話を聞いていると、客観的にみて可能性が低いな、と思うことがある。しかし、ダメだからといって、ダメだと言わない。ダメだと言ってはいけない。だからといって、できると言えばそれはただのお世辞になってしまう。先ずは可能性が低くても、本人がそれを望んでいるのなら、まず望んでいることを認めることだ。人は望まなくては得られないのだ。望むから努力もするし、努力をすれば可能性も真剣に考えるようになる。そもそもすぐに手が届くような希望なんて希望ではない。少し無理くらいなのを、ひとつひとつ課題をこなし、困難を乗り越えることに意味があるのだ。ダメだからダメだとは言ってはいけないのだ。やってみましょう、やりましょう、そこからしか挑戦は始まらない。挑戦を続けると能力も上がるのだ。平凡が非凡になれるのだ。
戦いの始まり
また戦いが始まる。ここからが本番だ。講習中は疲れはてていたが、十分に休養できた。こんなに気持ちが穏やかになるまで、体も、心も、神経も休めたことはとてもうれしい。これからギリギリの戦いが続く。それでもやる。やり抜く。
話の聞き方 些細なことでも褒める
どんな些細なことでも、その人が成長していたら褒めよう。人は些細な成長は本人ですら気が付かないことがある。そういうときに、こういうことができるようになったね、と褒められると気が付かない成長を明確に認識できる。また、ほんの些細な成長でも見てくれている人がいることが励みになるし、勇気も湧く。ただ、些細な成長を褒めるためには普段から人をよく観察し、人の心の動きが直観でわかる力を磨いておく必要がある。
焦らないということ。
限られた時間のなかで結果を出す。でも、焦ったらいけない。焦らない。本当に大切なことを焦らないで、じっくりやっていく。自信をちょっとずつつけていく。ほんのちょっとの自信でも、焦らないで積み上げたものはこれで大丈夫だという静かな確信になる。ちょっとずつの静かな確信はある時、勢いになる。急ぐ時ほど焦らないこと。じっくりやることだ。
智恵
僕の仕事は次から次へと送られてくる問題を素早く、忍耐強く解決していく力が必要だ。恐らく、この業界での仕事ひとつひとつをしっかり経験して、仕事全体が見えることが学ぶべきことだ。仕事全体とは何か?というと、いいものをつくること。いいものをつくったら必ず売り切ること。いいものを売ったら顧客から喜んでもらった上で代金を払ってもらうこと。この3つだ。簡単なのだ。いい人を採り、ていねいに育てあげること。育てたら、顧客を開拓して、契約し、コマを埋めること、そして、いい授業を提供し、顧客から喜んで代金を請求、支払ってもらうこと。具体的にはこの3つ。そのひとつひとつに智恵を積み上げていけばいい。マニュアルももちろん必要だ。しかし、マニュアルだけでは足りない。経験と智恵がいるのだ。
安らぐということ
生きることは苦しみの連続だ。逃げずに、前を向いて、誠実に、日日起こることに対処していくと、相当の辛さを耐え忍ぶことが必要だ。だが、その苦しみの連続にふらふらになりながら、じっと向き合い、目前のひとつひとつを解決していくと、そこに貴重な安らぎを得ることができる。何も起こらない、何も起きない、しないことで得られるものではない。為すべきことを為すことで得られるものだ。それが本当の恵みなんだ。苦しみに耐えに耐えに耐えていくと、あるときもうこれでいいよ、というところにくる。その時ほんの一瞬だけ心が安らげる場所に行くことができるのだ。そして、しばらく安らいだら、次の試練に立ち向かうのだ。
話の聞き方 励ます
話をただひたすら聞くこと。そして、相手の本当に望んでいるものが出てくるのを待つ。その上で、相手が否定的な思いや、破壊的な考えがあればそこは同調したらいけない。否定的、破壊的な考えを選ぶということは、否定的、破壊的な行動に進んでいくからだ。人はその人が考えた通りの人生を歩むことができる。破壊的な考えは破壊的な行動を選ばせる。また、破壊的な行動は破壊的な結果を生む。だから、粘り強く、粘り強く相手の破壊的な、否定的な考えに異を唱えるのだ。やんわりと、優しく、でもね、と。破壊的な考えに同調すると話ははやく進んでいく。怒りや、不満、愚痴、悪口は人を興奮させる。しかし、その興奮はその人の心を確実に破壊し、マイナスの毒汁を出し、からだと精神を酸のように溶かしてしまうのだ。破壊的否定的な考えに同調することは、そのひとのからだと精神を傷つけることに加担していることなのだ。だから、でもね、そんなことないよ、と粘って粘って励まし続けるのだ。
話の聞き方 その2
人の話を聞くにはこつがある。まずはひたすら誠実に相手の話を聞くこと。そして、もうひとつは自分の意見は言わないことだ。人は自分の人生は自分で決めるものだ。たとえ、日常の些細なことでも人は自分のしたいようにしたいのだ。ただひたすら話を聞いていると、この人はこうしたいんだな、という方針がわかってくる。そして、その人の方針に沿って話を合わせていけばいい。その時自分の意見は押さないようにしよう。言っても、こういう考えもあると例示するにとどめよう。
話の聞き方
話の聞き方にはいくつかこつがある。一つは、その人の目を見て、優しい気持ちでしっかりと聞くことだ。それが人の話を聞くすべてと言える。自分のことは自分にしかわからないものだ。だから、他人が意見を言う必要はない。相手にできるだけ誠実な姿勢で、和やかに聞いていればいい。時間は気にしないこと。いくらでも聞いてあげる。すると、始めに話していたことと、本当に話したいことは少し違うことに気づくはずた。どんなに親しい間柄でも、すぐに本題に入れるわけではない。やはり、話の核心をすぐには話せないのだ。この人は私の話をしんけんに聞いてくれるな、受け入れてくれるな、信用できるな、と思えてから初めて本当に言いたいことを話してくれるのだ。相手が本当に話したいことを話始めたら、相手が本当に納得できるように話を誘導すればいい。その時決して自分の意見は言わないのがいい。あくまでもその人の結論に合わせてあげるのだ。
暑いときは暑い暑いとグダグタ言わない
夏は暑い。暑いときは、熱いからどうしたの?とか暑いから頑張りましょう!とか、夏は暑いのだから、暑いと言わないのがいい。それが夏の正しい考え方だ。人間は言葉で思考している。やるぞ!という言葉で考えていれば、やるぞ!という思考になって行動もまた、やるぞ!という行動になる。反対に、だめだー。という言葉で考えていれば、だめだー。という思考になって行動もまた、だめだー。という行動になる。だから、暑いですねー、こういうときは何にもやる気になりませんね~、なんて言ったら絶対だめなのだ。暑い、暑いなんて言ってないで、さっさと目の前にある仕事を精一杯しっかり片付ける。この人といると、暑いなんて忘れてしまうな~、っていうところまで行く。それが夏の暑いときの正しい身の処し方だ。